製品例詳細情報
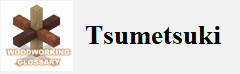
●爪付きナット
2枚の金属製の板材を最も簡単に接続固定しかつ接続解除もできる方法を考えてみてください。
おそらくもっとも簡単な方法は、2枚の金属製板材に穴を開けボルトとナットで締結することではないでしょうか。
アナ部分に座繰りを入れてボルト頭部やナットを隠すことをすれば、より見た目は良くなります。
それでは次に金属製の板材ではなく、2枚の木製の板材を最も簡単に接続固定しかつ接続解除もできる方法とは何でしょうか。
金属製の板材の場合と同様に、ワッシャーを選択して2枚の木製板材に穴を開けボルトとナットで締結することで対応はできるかもしれません。
直感的には強い締結は難しいかもしれないという不安が残ります。
このような場合、爪付きナットとボルトの組み合わせという選択肢があります。
Photo. 1 をご覧ください。
写真左が、爪付きナットです。
内部にネジを切りナット状に加工された円筒とその円筒のつばに爪を付けた形状をしています。
写真右が、使用例です。
板材に円筒の外径を入れる通し穴を掘り、爪付きナットのつばを隠すため座繰りをいれてます。
写真左の爪付きナットを裏返し、穴部に挿入しつばに上部から下向きの圧力をかけつばの爪を木部に食い込ませ固定させます。
つなぐ相手の板材にボルトを通す通し穴を掘り込み、両者の穴を合わせてボルトと爪付きナットを締結すれば完成です。
写真右には存在した爪付きナットのつばを隠すため座繰りを省略しても見栄えは良くないですが機能的には問題ありません。
使用頻度の高い爪付きナットはホームセンターで入手できます。
Photo. 1 爪付きナット(写真引用:http://kappahanbesuki.blog94.fc2.com/blog-date-20150107.html)

●天板(てんぱん、てんいた)
箱物の構成ご参照

●留め(とめ)、留め接ぎ
箱物で板材を直交させて接合する場合、Photo.1 に示しますように接合する木口を直角ではなく45度にして木口同士を密着させて接ぐ仕口を留め(とめ)あるいは留め接ぎと呼びます。
こうすることで木口を外側に出さずに組むことができます。

Photo. 1 留め接ぎ (写真引用:https://blogs.yahoo.co.jp/jirakudou001/35426779.html)

●貫(ぬき)
テーブルやいすといった脚物家具の脚部をつなぎ合わせて補強するための水平方向の部材を貫(ぬき)と呼びます。
多くの場合、貫は脚にほぞで接がれます。
建築用語では、木造建築の柱と柱を貫(つらぬ)いて構造的に固める横材を貫(ぬき)と呼びます[S2]。
貫の原意は、ここからきているものと考えられます。

●箱物の構成
箪笥、チェストなどの箱物の構造は、Photo. 1に示すように天板、側板、地板、台輪から構成されます。

Photo. 1 箱物の構成 (写真引用:https://item.rakuten.co.jp/kiriyasan/c/0000000352/)

